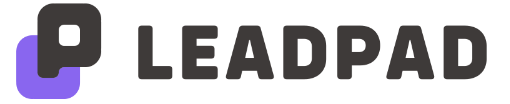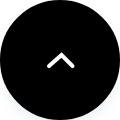インテントデータとは?購買意欲を可視化して営業成果を爆上げする方法を解説
BtoB営業の現場では、「どの企業が今、購買を検討しているのか」をいち早く見極めることが成果を左右します。近年、その判断を支える指標として注目を集めているのが インテントデータ(Intent Data) です。
顧客の行動データから購買意欲を読み取り、商談の確度を高めるこの仕組みは、営業・マーケティング双方の生産性を劇的に改善します。
本記事では、インテントデータの基礎から活用のメリット、導入における課題、代表的なツールまでを体系的に解説します。
目次[非表示]
インテントデータとは?基本と注目される背景
インテントデータの定義(購買意欲を示す行動データ)
インテントデータとは、ユーザーの購買意欲や関心度を示す行動データ の総称です。例えば、以下のようなオンライン・オフライン行動が該当します。
特定の製品カテゴリに関する記事を頻繁に閲覧している
セミナーやウェビナーへの参加履歴がある
ホワイトペーパーを複数回ダウンロードしている
比較サイトで製品を検索している
SNSで関連キーワードを投稿・フォローしている
これらの行動を解析することで、まだ顕在化していない「購買意図(=インテント)」を読み取ることができます。従来の「リードスコアリング」よりも一歩進んだ、行動に基づく購買予兆分析が可能になるのが特徴です。
インテントデータの種類(ファースト/セカンド/サードパーティ)
インテントデータは、取得元と活用範囲によって大きく3種類に分類されます。それぞれの特徴を理解することで、自社に最適なデータ活用戦略を構築できます。
データ種別 | 定義 | 取得元 | 特徴・活用ポイント |
ファーストパーティデータ | 自社が直接取得したデータ | 自社Webサイト、MAツール、メール、アプリログなど | 信頼性が高く、個々の顧客行動を詳細に追跡できる。CRM連携に最適。 |
セカンドパーティデータ | 他社が収集したファーストパーティデータを、パートナー契約などを通じて共有・利用するもの | 業界団体、メディア企業、比較サイト、提携プラットフォームなど | 共有元が明確なため信頼性が高い。自社データの不足を補う“拡張データ”として活用。 |
サードパーティデータ | 外部データプロバイダーが複数の情報源から収集・販売するデータ | 比較サイト、広告ネットワーク、Cookieデータなど | 業界全体の傾向や潜在顧客層を把握できる。スケール拡大に強みがあるが、精度管理が課題。 |
データの組み合わせによるシナジー
近年のBtoBマーケティングでは、ファーストパーティ+セカンドパーティ+サードパーティを組み合わせた「ハイブリッドデータ戦略」が主流になっています。
例えば
自社の顧客行動(ファースト)+業界メディアからの閲覧データ(セカンド)
さらに市場全体のトレンド(サード)を加味してスコアリング
このように、データの深さ(精度)と広さ(網羅性)を両立させることで、より正確に購買意欲を把握できるようになります。
BtoB営業でインテントデータが注目される理由
BtoB営業でインテントデータが急速に注目される背景には、以下のような市場環境の変化があります。
1.購買行動のオンライン化
コロナ禍以降、企業の情報収集や検討プロセスは大部分がオンラインに移行しました。購買担当者は営業担当者と接触する前に、すでに70%以上*の意思決定プロセスを終えていると言われます。
出典:Findings from 6sense Research: When Do B2B Buyers Reach Out to Sales?
2. 従来のリード獲得手法の限界
展示会やテレアポなどの量的アプローチでは、購買意欲の低いリードが混在し、営業効率が低下します。インテントデータを活用すれば、「今、情報収集中の企業」 に的を絞ったアプローチが可能になります。
3. データドリブン営業の浸透
CRM・MAツール・SFAの普及により、営業・マーケティング活動がデータ化されました。インテントデータはそれらを補完し、「顧客の動き」そのものを見える化する 役割を果たします。
インテントデータ活用のメリット
インテントデータの活用が注目される理由は明確です。それは「顧客の行動を理解し、最も効果的なタイミングで最適なメッセージを届けられる」からです。これまで勘や経験に頼っていた営業・マーケティング活動が、データを基盤とした“科学的なアプローチ”へと進化します。ここでは、その主なメリットを3つの観点から詳しく解説します。
商談化率・成約率を高める効果
インテントデータの最大の強みは、購買意欲が高まっている企業を早期に見つけ出せる点です。従来のリードリストでは、興味関心の低い見込み客にまで営業リソースを割く必要がありました。しかし、インテントデータを活用すれば、すでに情報収集を始めている企業や、競合製品を比較検討している企業などを特定できます。
営業担当者は、温度感の高いリードから優先的にアプローチできるため、商談化率や成約率が飛躍的に向上します。
マーケティングROIや広告効率の改善
インテントデータは、マーケティング活動全体のROI(投資対効果)を高めるうえでも大きな効果を発揮します。特に広告配信やコンテンツ戦略においては、購買意欲の高い層だけに集中してリーチできるため、無駄な広告費を抑えながら高い成果を得ることができます。
例えば、自社の製品カテゴリに関連する検索行動を頻繁に取っている企業を特定し、その企業向けにカスタマイズした広告を配信する。これによりクリック率やCVR(コンバージョン率)が上昇し、同じ予算でもより高いリターンを実現できます。
また、閲覧傾向や検索キーワードをもとに興味関心を可視化すれば、どのテーマのコンテンツが効果的かも判断可能です。こうしたデータをマーケティングオートメーション(MA)に組み込むことで、見込み客の行動に応じたメール配信やコンテンツ提供が自動化され、結果としてROI全体が底上げされます。インテントデータは、マーケティングの「打率」を上げるための最強のデータ基盤と言えるでしょう。
顧客体験(CX)向上とLTV最大化
インテントデータの価値は、獲得フェーズにとどまりません。購買意図の把握は、既存顧客のロイヤルティ向上やLTV(顧客生涯価値)の最大化 にも貢献します。
具体的な活用イメージ
既存顧客が新しい関連製品の情報を検索し始めた段階でアップセル提案
利用状況データと合わせ、解約リスクの高い顧客を早期に検知
個々の興味関心に合わせたメール・広告・コンテンツを配信
こうした施策により、「押し売りではなく、タイミングの合った提案」が可能となり、顧客満足度が向上します。結果として、リピート率・LTVの向上に直結するのです。
インテントデータ導入・活用における課題
インテントデータは営業・マーケティングの大きな武器になりますが、導入すればすぐ成果が出るわけではありません。ここでは、導入・活用を進めるうえで押さえておくべき代表的な課題を整理します。
データ収集の難しさと情報の精度問題
まず最初に直面するのが、「どのように正確なデータを収集・選別するか」という課題です。インテントデータは膨大な行動ログから生成されますが、その中には誤ったシグナルやノイズも多く含まれます。
例えば、同一企業内の別部署による検索行動や、リサーチ目的のアクセスなど、実際の購買意図と関係のない行動も検出されてしまうことがあります。
特にサードパーティデータでは、収集元の透明性や更新頻度が不明確な場合もあり、「データの鮮度」と「信頼性」 が課題になります。精度の低いデータに基づくアプローチは、誤ったターゲティングや営業のムダ打ちを招き、逆効果になりかねません。そのため、導入段階では「データの収集元・更新サイクル・匿名化プロセス」を慎重に見極める必要があります。
属人的な運用・分析に依存してしまうリスク
次に多い課題が、「データの運用・分析が属人化してしまう」ことです。多くの企業では、インテントデータを導入しても実際の運用が一部のマーケ担当者やデータアナリストに依存しています。その結果、データの解釈や優先順位づけが担当者の経験や主観に左右され、再現性のある運用が難しくなります。
特に営業現場との連携が取れていない場合、マーケティング側が抽出した「購買意欲の高い企業リスト」が、実際の営業現場で活用されないというケースも少なくありません。
この課題を解決するには、データを分析結果として終わらせず、営業戦略・顧客管理のプロセスに組み込む仕組みを整えることが不可欠です。社内のナレッジ共有やデータリテラシー教育も、インテントデータ活用の成功には欠かせません。
ツール未整備による現場定着のハードル
最後の課題は、「ツールが整備されておらず、現場で使いこなせない」という点です。せっかく高精度なインテントデータを導入しても、それを営業担当者が手軽に閲覧・活用できなければ意味がありません。
特に、データが複数のツールに分散している場合(MA、CRM、SFAなど)、現場では「どの情報を信じればよいのか」が不明瞭になります。この課題を乗り越えるには、“使いやすさ”を意識したUI/UX設計や自動化機能の導入が鍵になります。
インテントデータの具体的な活用方法
インテントデータの真価は、「どのように使うか」で決まります。購買意欲を把握するだけでなく、営業・マーケティング両面で戦略的に活用することで、リードの質を高め、アプローチの無駄をなくせます。
ここでは、実務での3つの代表的な活用パターンを紹介します。
見込み顧客の検知と優先度付け
最も基本的な活用方法は、購買意欲の高い見込み顧客を検知して優先順位をつけることです。従来の営業では、問い合わせや展示会の名刺交換といった「表面的な接点」に依存していましたが、インテントデータを利用すれば、企業の検索行動や閲覧傾向を分析することで、購買意欲の高まりを早期に察知できます。
例えば、「SaaS 導入 コスト」「クラウドセキュリティ 比較」などのキーワードを繰り返し検索している企業は、導入検討段階にあると判断できます。こうした情報をもとにリードスコアを設定すれば、営業チームは今動くべき顧客を的確に見つけ出すことができます。
最適なタイミングでの営業アプローチ
営業成果を最大化するためには、「誰に」よりも「いつ」接触するかが重要です。インテントデータを活用すれば、購買行動が加速する瞬間を捉え、最も効果的なタイミングでアプローチできます。
具体的には、次のようなシグナルを把握することでタイミングを見極めます。
検索行動の急増:特定の製品カテゴリに関する検索回数が増加している
コンテンツ閲覧の集中:製品比較ページや事例記事を複数回閲覧している
外部イベント参加:関連ウェビナーや展示会への参加履歴がある
これらの行動変化は、企業が「課題を明確に認識し、解決策を探し始めた」サインです。この段階で営業が接触すれば、競合よりも早く信頼関係を築き、商談の主導権を握ることができます。つまり、データに基づいたタイミング戦略が、成約率の高い営業活動を可能にするのです。
パーソナライズされたマーケ施策(1to1マーケティングとの連動)
マーケティング領域では、インテントデータを活用することで、顧客ごとに最適化されたコミュニケーションが可能になります。見込み顧客の行動や関心を分析すれば、メール・広告・コンテンツなどを個別最適化し、今その顧客が知りたい情報を提供できます。
例えば、コスト削減に関心を示している企業にはROI改善の事例記事を、セキュリティ強化を重視している企業には安全性訴求の資料を送るなど、関心テーマに合わせたアプローチが有効です。このような1to1施策をMA(マーケティングオートメーション)やCRMと連動させることで、マーケティングと営業の連携がより強化され、結果として顧客体験(CX)全体の質が高まります。
インテントデータを活用できるツール選びのポイント
インテントデータを戦略的に活用するためには、適切なツールの選定が不可欠です。同じ「インテントデータツール」でも、提供範囲・データの鮮度・操作性・連携性が大きく異なるため、自社の営業・マーケティング体制に最も合うものを見極める必要があります。ここでは、ツール選びの主要なポイントを解説します。
データ網羅性と鮮度の高さ
まず確認すべきは、どれだけ広く・新しいデータをカバーできているかという点です。購買意図を把握するには、企業の検索行動・閲覧履歴・外部メディアでの活動など、さまざまな行動ログを統合的に捉える必要があります。そのため、ツールによっては特定業界や地域に強みを持つものもあれば、グローバルデータを扱うものもあります。
データの鮮度も極めて重要です。購買意欲は時間とともに変化するため、更新頻度が低いツールでは「過去の行動」を追ってしまうリスクがあります。理想は、週単位または日単位でデータが更新されるプラットフォームを選ぶことです。最新の行動データに基づけば、営業判断の精度が格段に上がります。
CRMやSFAとの連携による効率化
インテントデータの価値を最大化するには、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援ツール)との連携が欠かせません。データを単体で閲覧するだけでは、顧客理解が断片的になってしまいます。しかし、既存のCRMやMA(マーケティングオートメーション)と連携すれば、インテントデータを営業アクションに直結する情報として活用できます。
例えば、SalesforceやHubSpotなどと連携すれば、
CRM上で「購買意欲の高いアカウント」が自動的にタグ付けされる
SFA上で「優先アプローチリスト」が自動生成される
といった運用が可能になります。このように、データを「見える化」するだけでなく「動かす」仕組みが重要です。
インテントデータの代表的なツール
現在、インテントデータを活用できるツールは国内外で数多く存在します。しかし、BtoB営業やマーケティングの現場で実際に成果を上げているのは、データの精度・営業支援機能・連携性を兼ね備えたプラットフォームです。ここでは、国内外の代表的なツールを整理し、それぞれの特徴と強みを紹介します。
ツール名 | インテントデータの種類 | 主な特徴 | 強み | URL |
LEADPAD | ファーストパーティデータ | 受注率の高い企業を見つけるセールスオートメーションプラットフォーム。 | 160万社の企業データを活用したターゲット分析やタイミングキャッチ(購買シグナル検知機能)に特化。CRM連携も可能。 | |
Sales Marker | サードパーティデータ | 日本国内企業のWeb行動データを基盤としたインテント解析ツール。購買検討中の企業を「匿名状態」でも特定できる。 | 国内BtoB市場に最適化されたデータ精度と営業リスト生成の自動化。MA・CRMとの高い親和性。 | |
Bombora | サードパーティデータ | 世界的に最も利用されるBtoBインテントデータプロバイダー。複数の外部サイトから行動データを収集し、グローバル分析が可能。 | サードパーティデータの網羅性と国際的なBtoBカバレッジ。海外展開企業に適する。 |
まとめ
インテントデータは、顧客の「今まさに知りたい・買いたい」という購買意欲を可視化し、営業とマーケティングの精度を高める革新的な仕組みです。
感覚や経験に頼らず、行動データに基づいて最適な顧客へ、最適なタイミングでアプローチできる点が最大の魅力といえます。さらに、Sales MarkerやLEADPADなどのツールを活用すれば、リード検知から提案、顧客育成までを自動化し、営業成果を継続的に伸ばすことが可能です。
これからのBtoB営業では、「データを読む力」が競争優位を左右します。今こそ、インテントデータ活用の第一歩を踏み出すときです。